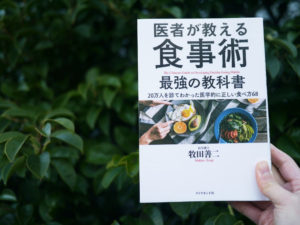仲春のころ、銘にぴったりの春の言葉
今回は3月中旬〜4月上旬、
花々が咲き、あたたかくなって様々ないのちが動き始めるこの時期に、
銘にできる言葉をあつめてみました。
(二十四節気では「啓蟄」「春分」のころ)
初桜(はつざくら):春の季語
その年に初めて咲いた桜のこと。
初花と同義ですが、初花よりも植物であることに重きが置かれます。
朧月夜(おぼろづきよ):春の季語
おぼろにかすんで見える月夜のこと。
水蒸気がやわらかくたちこめたまま夜になると
薄絹につつまれたようなぼやっとした月が見える。
三春で使える言葉です。
春光(しゅんこう):春の季語
もともとは春の風光、春の景色をいったが、春の日の光としても用いられます。
春の光、春景色、春の色などが子季語。
こちらも三春で使える言葉となります。
春雷・春の雷(しゅんらい・はるのらい):春の季語
春に鳴る雷を春雷、または春の雷と呼びます。
ひと鳴り、ふた鳴りほどでやむ短い雷の音。
とくに初めて鳴る春雷を初雷と、あるいは冬ごもりの虫を起こす、虫出しの雷とも。
春暁(しゅんぎょう):春の季語
春の夜明け方のこと。
夜が明けようとしているが、まだ暗い時分のことを春暁といいます。
曙(あけぼの)は暁(あかつき)よりやや時間的に遅れ、夜がほのぼのと明けようとするころのこと。
他にも、吉野山・初蝶・花霞・ 花明り など
茶杓とは?
茶杓とは茶道で使う道具。
茶器に入ったお茶をすくって、お茶碗に移すときに使います。
お茶道具には、お茶碗や茶杓などに銘がついてるものがあります。
お茶会などで使われる道具には大体銘がついています。
作者の想いだったり、道具の形に由来していたり、季節のものだったり。
お稽古では、銘を自分で考えてつけます。
これは季語や和歌に歌われるような言葉や、
禅語を覚えるための良い練習になります。
季節の言葉について参考にしている書籍
季節のことばについては、以下の書籍を参考にしています。
二十四節気と七十二候の季節手帳
さまざまな季語の本がありますが、「二十四節気と七十二候の季節手帳」は、きれいなイラストと、書かれていることばの解説が丁寧なので好きな本です。
茶の湯の銘 大百科
「茶の湯の銘 大百科」はその名の通り、百科事典としてお茶をしている人なら手元に置いておくと参考になる書籍です。
五十音順、月別、道具別、四季別と、銘の引き方も多く、ぱらぱら見ているだけでも美しい日本語を知れて勉強になります。
高価ですが、それだけ本当にたくさんのことばが載っているのでおすすめです。